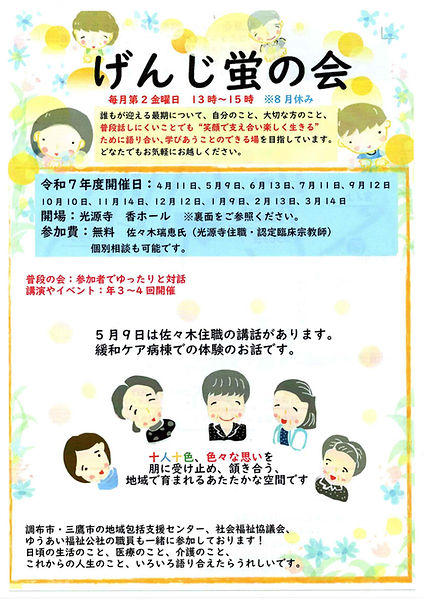東京都調布市 浄土真宗本願寺派 光明山 光源寺

TEL 03-3300-0881


光明山光源寺の沿革
山城国愛宕郡下京(現・京都府下京区)の「東の坊」住職であった
佐々木専祐師が、江戸幕府開府(一六〇三年)後間もなくの
一六一五(元和元)年、江戸浜町に寺基を置いたのがはじめです。
一六五七(明暦三)年、江戸の大半が焼失したと言われる
「明暦の大火(振袖火事とも称される)」によって、浅草横網に
存した本願寺浅草別院とともに被災したことから
別院と相まって築地に移転しました。一九二三(大正十二)年、「関東大震災」により築地別院とともに再び消失
一九二八(昭和三)年、東京市の区画整理にともない転出を余儀
され、東京府北多摩郡神代村字金子向台一二三〇番地に移転し、
現在に至っています。

浄土真宗の仏事としきたり
荘厳(おかざり)のしかた
仏壇の荘厳(おかざり)のしかたは、各派によっても多少異なります。また、法要の種類によっても違ってきますので、住職に相談するとよいでしょう。浄土真宗��では本来、位牌を用いる習慣はなく、それらは礼拝の対象ではないので、仏壇には置かないようにしましょう。位牌を用いないのは、それらに故人の霊がやどっているのではないかという、あやまった観念を抱き、浄土真宗の絶対他力の教えをくもらせるおそれがあるという理由からです。
浄土真宗の葬儀・法要の意味
仏事というと、死者の冥福を祈り、仏を供養し、僧侶に施しをすることであると考えられてきました。これは江戸時代以降、死者のための年忌法要が仏事の中心となり、そのために死者の追善のための行事と考えられるようになったからです。しかし、浄土真宗では年回法要(年忌法要)は故人をしのぶとともに、自らも仏法を聴聞し、仏恩に感謝する行事として行われるものであります。親鸞自身「親鸞は父母の孝養(きょうよう)のためとて、一返にても念仏申したること、いまだ候はず」(「歎異抄」より)と、亡き人への追善の供養のために念仏をとなえたことはないと述べています。

縁あるいのちを真実世界へと導くためには、まずもって、私が仏となる道を歩むことが肝要であり、その意味で仏事は阿弥陀仏のお慈悲を仰ぎ、仏法を聞く縁としてのぞむべきであります。葬儀も、亡き人に永遠の別れを告げるための儀礼ではなく、阿弥陀如来の願力によってふたたび浄土で会えるという思いを確かめあう法会であります。葬儀には昔からさまざまな迷信があり、現在にもそのまま伝えられているものがあります。たとえば日の吉凶、守り刀、逆さ屏風、魔除け、死装束、六文銭、塩をまくなどです。浄土真宗ではこうした迷信は一切必要ありません。
『再び会える世界』
どんなに名残惜しくても、私たちの世界には死による別れがあります。生・老・病・死。愛しい方との死別。避けられないこの現実に直面しますと、押さえきれない悲しみと悔しさが込み上げてまいります。
変化する現実。愛しい方もまた、その道理の例外ではありませんでした。大変に辛いことですが、この現実をしっかりと受け止めた時にこそ、『いのち』のあることの意味がかみしめられてくるに違いありません。
阿弥陀如来は、『心配しなくていいよ。いつでも、どこでもあなたを離さないよ。共に仏になるための人生を歩んでおくれ』と、生と死に戸惑い、四苦八苦しながら生きる私たちを、限りない慈悲で南無阿弥陀仏の喚び声となって、お浄土へとお導き下さいます。
亡き人は、阿弥陀如来に抱かれてお浄土に往き生まれ、み仏となっていかれたと受けとめさせていただきましょう。そして、常に私の側に寄り添い、この限りある『いのち』の意味を、問い続けて下さるお方であると偲んでまいりましょう。そこに亡き人をご縁として、大切なことに気づかせていただく『再び会える世界』が開かれてまいります。
『法名について』
阿弥陀さまのみ教えに帰依した方につけられる名前のことです。
浄土真宗では、親鸞聖人が「釋親鸞」となられたことにならって、お釈迦さまの「釋」の字をいただいて「釋〇〇」とつけられます。それは仏弟子の一人に加えさせていただいたことを意味します。
生前に法名を受ける機会(帰敬式)の無かった方は、葬儀の時に住職よりいただきます。
『とらわれてはならない俗信・迷信』
地域により、葬儀に際して様々な言い伝え・俗信・習慣があります。友引・神棚かくし・清め塩・死装束・六文銭・逆さ屏風・守り刀・一膳飯など。これらは皆、亡くなった方を穢れたものとして扱う非礼な心から生じたものです。
お念仏の心をいただくものは、これらのことにとらわれることなく、葬儀をつとめることが大切です。
お知らせ
各記事をクリックしてご覧ください。詳細が表示されます。


アクセス

〒182-0006
東京都調布市西つつじヶ丘2-30-11
TEL:03-3300-0881
[ 駐 車 場 ] 数台分あり。
周辺の駐車場をご利用ください。

道案内
①京王線「つつじヶ丘駅」より徒歩12分
②京王線「つつじヶ丘駅」北口から「杏林大学」行き
バスにて「中西」下車、徒歩1分
③京王線「つつじヶ丘駅」北口から「深大寺」行き
バスにて「西つつじヶ丘1丁目」下車、徒歩5分